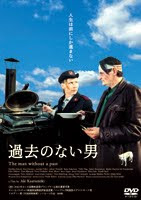昨日の記事にあるO高君であるが、本当の高は「はしごだか」だったことが今朝分かりました。実際は、「髙」であったわけで、なんか申し訳ないことをしたような気持ちになりました。
名前については、それぞれ使用する漢字にも意味があり気をつけてはいるのだけれど、名字はもうすでにあるものの意識が強く、名前ほどは良く確認していないことが多いのです。本当に失礼な話だと思いますが、僕自身も初めての人に名前を正確に呼ばれることは少なかったこともあり、それについてはあまり気にもかけていなかったことがそうさせているのかもしれません。
ワープロやPCで文字を入力するようになってからは、特に名前だけではなく、あらゆる漢字が書けなくなってきている気がします。実際メモを取ったりする時に、漢字に迷い、ひらがなで書いていることが多くなりました。それでも、以前は読む方はそれほど苦もなかったのですが、最近は読みや変換した漢字ですらどの漢字を使うのかに迷うようになってきました。やはり、本や文章を読む機会が減り、かつ型どおりのビジネス文書ぐらいしか書かなくなったからかもしれませんね。
そんなわけで、このブログも少ないボキャブラリーの中で、自分が理解できる漢字でしか書かれていないと思います。もっと文才があり、より分かりやすい言葉を使って書けたら、どれほど世界が広がるかといつも思っています。
また記事を読み返していると、いくつか障害に関わるものがあります。ものごとの妨げとなる障害という漢字が、一般的に「障害者」に使用されているケースが多いですが、戦前は「障碍」との混同があり、当用漢字表により「障害」への書き換えが進んだそうです。現在、その「害」(負としてのイメージが強いのだと思う)の当て方を巡って、さまざまな分野で検討されているとのことです。
僕自身はその漢字以前に、あらゆる人(僕も含め)が「ショウガイシャ」だと思っていて、だからこそひとりで生きていくことが難しいと感じているので、どの漢字が適当なのかよく分かりません。だから、この人はこんなショウガイを持っているのに、とても凄いことをしているんだよと声高に言いたいのではなく、素直にその行為や表現に感動し、記事として載せているのです。見ているだけで、元気や勇気や前向きな力を貰えますから。
それにしても、日本語って、特に漢字はいろいろと当てられるので難しいですが、気をつけて使っていこうと改めて感じた次第です。そんな感じじゃ駄目です。
O髙君、電報を打つ時にはちゃんと伝えますので、許してね。
チョボチナイとコペン
5 日前